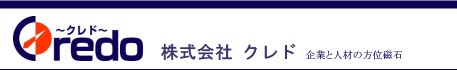『評価制度』の設計&運用

評価制度における人事考課とは1年間、もしくは半年・四半期など、一定期間の従業員個々人の勤務実態(勤務態度、職務能力、勤務成績)を評価することにより、従業員個々人の能力の特色、能力のレベル、能力の発揮度を把握するために実施されるものです。
具体的には人材の能力開発(CDP)、有効利用、賃金や賞与額の決定、昇進・昇格、適材適所の配置、自己啓発の材料などに使用することを目的としています。

- 見える結果ばかりを重視し、プロセス(過程)はとかく軽視されがち
- 考課者の主観的な人物評価やグループのなかで序列をつける相対考課になりがち
- 従業員のどのような行動を評価するのかについて体系的なルールがなく、考課結果の片寄り、従業員の不平・不満、モラールダウン等の原因となりがち
- 人事考課の結果が昇格、昇給、賞与などの処遇にどう反映するのかについて不明確のままになりがち

次のような要件を満たす必要があります。
- 人事考課の対象と目的に応じた考課要素の設定
- 人事考課者の適正な評定能力の保持
- 客観的かつ計量的な評価方式の採用
- 心情的・恣意的な判断の排除
- 定期的な人事考課の実施
実際の人事考課要素は企業ごとに多様に設定されていますが、一般的には職名や職階ごと
に評価要素を決定する必要があります。
対象別・目的別に評価要素を選定し、
- 職務遂行能力
- 職務達成度
- 勤務態度
- 将来の可能性や課題
などについて客観的、計量的に把握できるような評価要素と評価基準とを設定し、考課表を作成する必要があります。
これらをサポートいたします。

今まで、年に2回の人事考課を行っていましたが、上司からの指示でただ漠然とこなしてきていました。
そのため、部下には結果の説明も出来ずに、何となく秘密主義のようなイメージでした。
しかし、毎回の人事考課の前に人事考課者研修を受けることで徐々に何をどう評価したらいいのかがわかるようになりました。
部下との面談で結果の説明ができるようになって、コミュニケーションも随分とよくなりました。
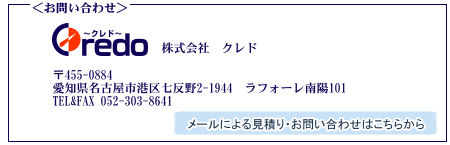
 
|